ラボにおけるERESとCSV【第84回】

国内企業に対するFDA 483に記載されたデータインテグリティ観察所見(Observation)の概要を紹介する。
FDA 483におけるデータインテグリティ指摘(54)
7.483における指摘(国内)
前回より引き続き、国内企業に対するFDA 483に記載されたデータインテグリティ観察所見(Observation)の概要を紹介する。
■ PPP社 2019/09/13 483 その5
施設:バイオ原薬工場
■Observation 4
B) pH計の管理番号がバッチ記録に記載されていない。また、pH計のプリントアウトにも管理番号が記録されていない。
★解説
どのpH計をGMP業務に使用したか識別できないために指摘されている。データインテグリティ要件であるALCOA+の「A:Attributable(帰属性)」が満たされていない。バッチ記録に手動で記録した機器管理番号よりプリントアウトに印字された機器情報の方が信憑性が高いのはいうまでもない。従って、プリントアウトに機器の管理番号もしくは製造番号/シリアル番号を印字できるのであれば、印字できるように設定しておくべきである。
この483への回答例として下記が考えられる。
- プリントアウトに機器の製造番号が印字されるようpH計を設定した
- バッチ記録にそのプリントアウトを添付し、どのpH計を使用したか識別できるようにした
FDAはこの回答例で満足するかもしれないが、当該機器に関する上記の対応に加え、GMP全体に対し以下のような再発防止策を規定しておくべきである。
製造記録および試験記録において:
- 使用した機器を特定できる情報を記録すること
- プリントアウトを記録に添付する場合、機器を特定できる情報をプリントアウトできる機器においてはそのように設定しておくこと
さて、2021/8/1より施行されている改正GMP省令に以下の記載がある。付記した逐条解説は改正GMP省令の運用課長通知からの抜粋である。
第八条 (手順書等)
第2項
手順書と記録について、その信頼性を継続的に確保するため、第二十条第二項各号に掲げる業務を文書により定めること。
(逐条解説)
医薬品製品標準書及びGMP省令第8条第1項の手順書並びに同令第2章に規定する記録について、継続的に信頼性(いわゆるデータ・インテグリ ティ)を確保するため、同令第 20 条第2項各号の業務の方法に関する事項を文書により定めることを要するものであること。この場合の継続的とは、それらの文書及び記録の作成時から保管期間が満了するまでの期間にわたって継続するとの趣旨であること。
第二十条 (文書および記録の管理)
第2項
手順書等及びこの章に規定する記録について、あらかじめ指定した者に次に掲げる業務を行わせなければならない。
一 手順書等並びに記録に欠落がないよう、継続的に管理
二 手順書等及び記録が正確な内容であるよう、継続的に管理
三 他の手順書等及び記録との不整合がないよう、継続的に管理
四 欠落、不正確、不整合に対する是正措置と予防措置
五 その他手順書等及び記録の信頼性を確保するために必要な業務
六 前各号の業務に係る記録を作成し、これを保管
(第2項の逐条解説)
手順書並びに記録の信頼性(いわゆるデータ・インテグリティ)の確保業務について規定。あらかじめ指定した者については、当該文書及び記録の種類、内容等に応じて、その信頼性確保に関して熟知している職員を責任者としてあらかじめ指定し、その職責及び権限を含め、文書に定めておくこと。医薬品の製造関連の文書及び記録の信頼性の確保については、PIC/Sガイダンス PI 041 “GOOD PRACTICE FOR DATA MANAGEMENT AND INTEGRITY IN REGULATED GMP/GDP ENVIRONMENTS” 等が参考になる。
(注記:「PIC/Sガイダンス PI 041」とはPIC/Sの査察官むけDIガイダンス)
(第2項第四号の逐条解説)
欠落があった場合又は内容に不正確若しくは不整合な点が判明した場合には、その原因を究明し所要の是正措置及び予防措置をとること
改正GMP省令の観点からすると、本483指摘に対する上述した対応例は以下の様に位置づけられる。
1) 483回答例は、第二十条第2項第四号が求める「是正措置」である
2) 再発防止策例は、第二十条第2項第四号が求める「予防措置」である
そして、これらは第八条第2項に従い文書化されねばならない。
2ページ中 1ページ目






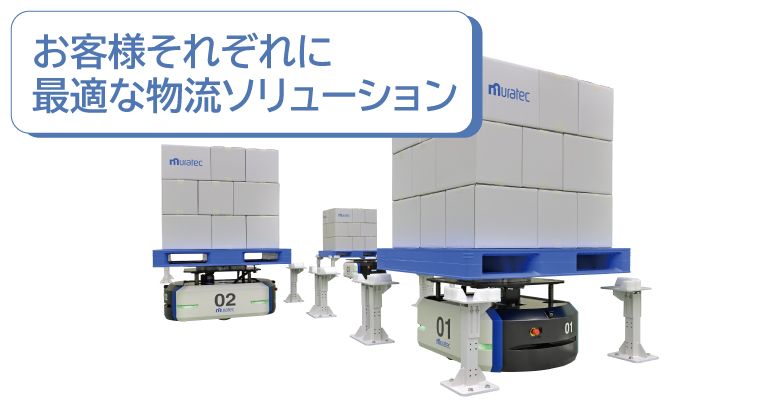








コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント