ゼロベースからの化粧品の品質管理【第25回】

今回は「規格外(OOS)管理書」に関する事項について解説をする。
化粧品GMP手順書の作り方 ⑦品質管理試験室(2/2)
毎月、化粧品の品質保証体制についてお話させています。今回は、前回の⑦品質管理試験室の中で、実務者の立場からすると実に悩ましい「規格外(OOS)管理書」に関する事項についてお話します。
少し本題から外れますが、ISO22716 の要求事項と監査において先日疑問を感じる事項がありましたのでお話します。
ある化粧品会社の現場を見せて頂いた際に、吸気口からの風の流れが、バルク作業者の背面から原料の投入口の方に向いて流れていました。そこで、“吹出口からの風の流れを変えるように邪魔板を付けた方が良いのではないか”と指摘させて頂きました。
この化粧品会社は、ISO22716 の民間認証を8年以上維持されている会社でしたので、GMP体制は問題ないとのことで、品質関連の部長さんから、
① 4.9.1 パイプ、排水管及びダクトは、滴または凝集水が・・・
と限定されており、風向は規定されていない。
② 5.3.2 機器は、材料、稼働機器、従業員の動きが品質リスクをもたらすことのないように・・・
となっており、原料の仕込み動きは一般的な動きで、品質リスクのある動きではない。
という話になり、過剰な指摘事項であるとのコメントを頂きました。
エアコン等の吹出口から吹出している空気は、芽胞菌や黒カビ等の真菌が検出されることが多いこと、人に付着した塵埃や毛髪等が落下した場合には投入口からバルクの中に入ってしまうことが懸念されることから、品質上で異物混入のリスクを感じます。そのため、品質リスク面から、例えば、吹出口の浮遊菌の状況を確認した方が良いこと、付着したゴミが投入口から入り込まないことを様々な状況でシミュレートし問題ないと判断された場合には問題ないとお伝えしました。も指摘時点では確認がされていなかったことから、品質リスクアセスメントの視点からは懸念事項として取り上げるべきであると考えます。
このような事例は時々あり、手順書類を作成する際に、要求事項に対して単に言葉を肉付けするのではなく、現在行っている手順に対して、「“GMPの3原則”の視点で考えること」、「懸念される事項はないか?」、「問題ないと説明できるのか?」 を考え、手順書を整えることが重要と考えます。
ISOの要求事項に対して、直接的な対応を漏れなく記載されていることが立派なルール、そのような会社が優秀な化粧品GMP会社であるという事には違和感があります。手順書類が整っていて、そのルールを徹底されていたとしても、常に芽胞菌が検出されるバルクの状況だったとしたらどうでしょうか?そもそも、そのルールが品質リスクを下げる視点が機能していないとすると問題であると考えます。但し、現実の監査において、ISOの要求事項の各条項の直接的な事項のみに対して行われていることが多いように感じます。
脱線しましたが、本題に戻り、規格外処理手順(OOS)について以下お話します。
1.規格外品の処理手順
1.1.手順書で書かれていない部分で重要な事項
① 試験担当者は規格外の結果が出た場合、自分の試験のミスと真っ先に考えて、
再試験を行い、表面的に繕いがちである。
② ラボノートを使わずに、メモ書きも原本であることの認識が徹底されず、
ラボノートは対外的に要求されることがあるため綺麗に書かれているべきであると考えがちである。
1.2.運営上の間違い
① 試験結果を試験責任者が内容について照査、判定を行われず、担当者の判定結果に対して
ただ承認するだけである。
② 不合格の判定を品質部門の責任者が行わず、試験担当者の判定結果をただ承認するだけである。
1.3.規格外の結果が出た場合の初期対応の留意事項
① 原料、包装材料で規格外品が納品された場合、検査担当部門から品質管理責任者に報告、
承認された結果について、受入れ担当部門のから、納品業者又は原料、包装材料製造業者に連絡
する。
本社等が資材発注や生産管理の業務を担当している場合には、品質管理部門から連絡する。
② バルク製品、最終製品において規格外品が発生した場合、品質部門は、速やかに関係部門に連絡する
と共に、製造・生産での逸脱事項の有無、検査における逸脱の有無について調査を指示する。
同時に、現物について、隔離、識別表示について品質部門が責任を持って管理する。
1.4. 識別及び隔離
① 原料、包装材料については、それぞれの受入れ担当者は、品質部門より規格外品との連絡を受けた
場合、速やかに規格外品に「規格外」等の表示、識別をし、隔離し、誤って使われないようにする。
② バルク製品、最終製品については、それぞれの保管管理責任者が品質部門より規格外品との連絡を
受けた場合、速やかに規格外品に「規格外」「使用禁止」等の表示、識別をし、隔離し、誤って
使われないようにする。
③ これらの事項は再試験、再サンプリング・再試験を行う前に行う。
2ページ中 1ページ目








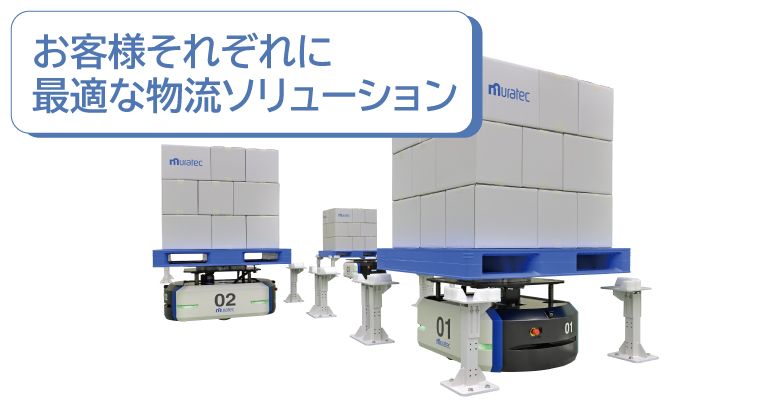






コメント
荒木 裕行 / 2022/10/08
毎回楽しみに拝見させて頂いております。今回は規格外に関する内容でしたが、規格内での対応事例についてお教え頂きたく思います。例えば、微生物検査において、通常の検査では検出されない状況が継続している中、菌検出結果があった場合、規格内であれば再検査もせずに出荷を進める、といった対応が化粧品業界では通例なのでしょうか。それとも、規格内であったとしても検出された菌の挙動を精査する為にも再検査を実施する、再検査後に規格内、品質上問題ないことが再確認出来た場合に出荷を進める、対応が通例なのでしょうか(私は後者の考えです)。また、USでは規格内の菌検出の場合に、上記の様な再検査を実施しての品質確認が許容されないとのお話を伺いました(FDAの考えとして、製造法に問題があることを認めていることに繋がり、その製造ラインで製造された全製品に疑義がもたれることになるとの内容)。再検査がUSでは許容されないということが本当にあるのでしょうか。上記の様に、初回の検査にて菌検出を認めた場合に、例え規格内であったとしてもその挙動を確認し、品質上問題ないことを精査することは品質を担保する上で必要と思う考えが一般的なのか否か、US含めた他国で一般的なのか否か、に関して、先生のご知見、ご経験、お考えをお伺いしたく思います。 大変お手数をお掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。
/
/
コメント